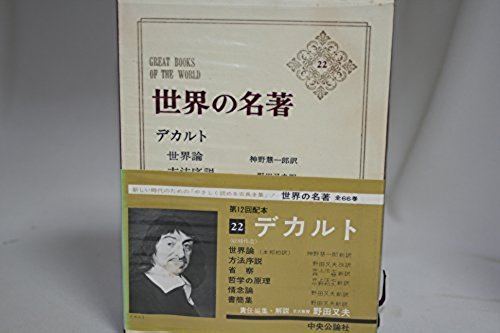『世界の名著〈第22〉デカルト』(中央公論社)
現在の中央公論新社に「世界の名著」という名高いシリーズ(全八一巻)があって、これについて思うと僕はこもごもの感慨をどうしても抑えられないのだ。どれだけ心拍数をあげて読んだか知れないよ。旧約・新約聖書も最初はこれで読んだ。パスカルの『パンセ』もモンテーニュの『エセ―』(抄訳なんだけど)もフロイトの『精神分析学入門』もデュルケムの『自殺論』もマルサスの『人口論』も勿論この叢書で初読した(この「初読」のサ行変格活用はいいね。新しくないか。歴史的用例だよこれは)。この叢書経験はそのまま「世界思想との出会い」だった。桁違いの知性との直面。知的豪傑からの呼びかけ。陳腐な物言いだけれど、「叡智」の存在に気圧されてしまうという経験は、人を否応なく謙虚にするのだ。「もう馬鹿の無知ですみません。あなたの叡智のお零れでもせめて」というふうな礼儀作法で書物に向き合わねば、人はついに何も得られない。
本叢書は「高校生でも読める」よう編集されていたらしいので(どこかの薄っぺらい「評論家」が高校生時代にこの叢書を読破したと吹聴していた)、訳文はいくぶん平明で、注釈も懇ろに記されている。結果ずいぶん広く普及した。「世界の名著」と言えば、読書人なら大抵一度ならず見聞きしているはずだ。すこし前の世代なら、感傷と懐古なしには語れぬ挿話が一つや二つ胸中に仕舞い込んであることだろう。
当然今でもよく見かける(もちろん古本ね)。知る限り高くても五〇〇円くらいで入手できる。発行されたのは凡そ一九六〇年代後半から七〇年代後半にかけてであり、たしかにいささか古くさい面もあって、たとえば「孫文/毛沢東」や「レーニン」などが堂々一巻組まれているところなどに少し「政治の季節」を嗅ぎ取ってしまうのだけれども、ぜんたいのラインナップは実に広汎重厚多士済済、いまでもじゅうぶん熟読に堪えるものだ。いったいバラモン経典からウィトゲンシュタインまでのコンテンツを広範に抑えているのだから、編纂者も力瘤のいれかたが違う。
とくに、四五巻のブルクハルト『イタリア・ルネサンスの文化』、五五巻のホイジンガ『中世の秋』、五六巻のマンハイムとオルテガ(『イデオロギーとユートピア』『大衆の反逆』)の出来具合は素晴らしかった。編纂の動機はどうあれ、これだけ質の高い著作群を廉価販売することの出版史的意義は極めて大きかったと思う。二十歳前後最初に手にしたハイデッガー集『存在と時間』の訳文には正直閉口したけれど、それはそれで痛快苦渋の洗礼に違いなかった(現在は岩波文庫から懇切丁寧な熊野純彦訳が出ている)。興に乗ってきたのでもうちょっと続けますよ。
個人的にでなくて世間的にも評判が高いのは、五九巻の「マリノフスキー/レヴィ=ストロース」ではないかな。抄訳だけど、当時『西太平洋の遠洋航海者』が訳出されたことの価値はなかなか大きかったと師匠がすこぶる褒めていた(今は文庫本でも種々読める)。
そしてデカルトの巻もなかなかよかったよ、というのが今回の趣旨なのだ。野田又夫の解説で、世界論、方法序説、省察、哲学の原理、情念論、書簡集がまとめて収録されている。要領のいいデカルト入門だね。岩波文庫で一冊づつ揃えるより、とりあえずここで主著はあらかた読める。僕もそのむかし熱心に読んだものだけど、特段訳文に不愉快を覚えることもないから、じゅうぶん人に推奨できる代物だね(尤も僕はひところ法政大学出版局のウニベルシタス叢書に鍛えられたおかげで、読みにくい訳文にも相当強くなっているのだけど)。もしアイドルの気違い染みたストーカー心理のごとく「自分はデカルト様に選ばれた」って気になれば、すぐにグーテンベルクプロジェクトのサイトから原語原文をダウンロードして精読研究すればいいのだ。人が本を選ぶのでなくて本が人を選ぶ。この際常識を翻然裏返すのだ。「お前は私を理解できる、いいか、耳の穴かっぽじってよく聞くんだ」、この曰く言い難い読書経験はいつの世にもあって、時空を超えた精神的師弟関係はこの契機を以て始まるのだ(そのことは内田樹が強烈なレヴィナス体験を通して熱弁をふるっている)。
デカルト(一五九六~一六五〇)は、今日的知見から見ると間の抜けたことも沢山考えている(もちろん今日的知見がぜんぶ「真」なのでもない)。とくに天体論や自然論にみるべきものは少ないけれど(歴史資料としては別)、彼の本源的な哲学姿勢、すこしでも疑い得るものは偽と見なし、すこしも疑いえない絶対確実の認識に立脚したうえで全ての思索をはじめようとするスタンスの開発・徹底は、ほとんど英雄的といってもいい(懐疑癖が肉体に沁み付いていない人間からすれば余程病的に見えるだろうが)。この懐疑がどんな過酷な段階を経るのかは読んでほしいですね。何につけネタバレは禁忌。彼の冴え渡る知性の一端を窺い知るのに、その論法のスリルを味わうに如くは無いのだ。
ところで、あらゆる人間のなかで僕は哲学者を一番尊敬している。自分の脳で底知れない世界と対峙している思索者に畏敬の念を抱かない人などあるものか。彼らは「何も分からない」という絶望の淵に立ったうえで思索を開始している。そこから踏みこむ一歩。それだけでもう格好いい。
アリストテレスもプラトンもエピクロスもニーチェもキルケゴールもフッサールもハイデッガーもサルトルも、皆凄まじく炯々たる眼光を持していたはずで、この眼光がまた底知れない愁いと勇気を湛えていたに違いないのだ。それに比べたら、政治的英雄などウンザリするほど粗野で愚鈍な俗物ばかり。何かひとつ属性というか呼称を選べるとしたら、何としても「哲学者」として死にたいものですね。「本物の知性」という部面からみると、哲学者以外は「話にならないだ。」いや本当に。
人は何のために生きているのか、という種類の問いかけは嫌いでないけど、そこに青春風を吹かした自己陶酔的ポーズが寸毫でも混じるのを見てしまうといつも、目いっぱい唾を吐きかけてこう罵りたくなる。
「意味みたいな不細工なものをいちいち了解している生物などいないぞ、この青二才め」
とはいえ(とはいえ、なんか随分久しぶりに使ったな)、「なんで」という問いには何か抗い難い色気というか、甘い蜜のような芳香があることは十分承知している。うんざりするほど。ただ僕は、この「なんで」を含んだ言明が世の中に満ち溢れている一方で、この「なんで」そのものの正体に切り込んでいる言明がおそろしく少ない事実に苦言を表明したいのだ。「なんで」そのものを哲学の対象にしないと、この問いに参入できないと思うのだ(一字でも節約できるので以下は「なぜ」に統一)
「なぜ」を含んだ文言は、何を以て最適解(至上解)としうるのか。荒っぽい言い方だな。「なぜ」の発問を十分に満たしる応答の条件があるとして、それはどのようなものであるのか。まだ荒っぽい。そもそも本質的に「なぜ」とは何か。これでは愚問の見本みたいじゃないか。うんとね、いま苦渋してまで何がいいたいかの一端でも示すためにはどう言えばいいかな(不愉快過ぎて掌に脂汗が滲んできた)。ようするに、「なぜ」という機能要素の「正当性」をいかにして把握するのか。駄目駄目。
「なぜ」という「言明要請」に応答しうる「最終言明」においては、いかなる「言明要請」の可能性をも認められないのか。ちょっと近づいたかな。
例えばこういうこと。「なぜこの宇宙は存在しているのか」という悪評高い発問(=言明要請)があります。なぜこれが「問題含み」かというと、発問受容者の解釈次第で、この「なぜ」はどのような様相をも帯び得るからである。
ある解釈者は、「この宇宙で生きる我々の使命」という目的論的テイストをあらかじめ与えているかもしれないし、ある解釈者は「自然科学的解答」(例えばインフレーション宇宙モデルとか)以外は全部言葉遊びだというスタンスからこの問いを受容するだろうし、またある解釈者は「無は論理的に自己否定概念であるから何ものかが存在していることは自明である」という種類の哲学的命題に立脚しているかもしれない。
当然その立場によってめいめいの「最終言明」の種類が大きく相違する(厳密にいうと、「統一的自己」のなかでさえ「単一の問い」などありえない。昨日の「なぜこの宇宙は存在しているのか」という問いと、今日の「なぜこの宇宙は存在しているのか」という問いとでは、受容の仕方において僅かに相違しているからである)。
同じ発問がそもそも様々な位相・含意で解釈されてしまうのだ。これはヒトのコミュニケーション行為においてはどうしても避けがたい事態なのだ。「問い」は決して「単一」ではない。「われわれ」は答える以前に問うことさえまともに出来ないくらい朦朧たる内省状況にある。常に「言葉の非同一性問題」に直面しなければならない。
考える者の多くは大体この段階で絶望する。だがここで諦めて発狂してはいかんぞ。全ての思考行為はこうした言語運用の危機的状況からようやく始まるのだ。
とりあえず重大な暫定命題をひとつ。
「ある発問に対して十全に応答しうる言明は存在しない」(≒発問を充足させる最終言明は存在しない)
なぜなら、発問の意味的構成要素は「単一解釈」を可能としないからである。
「なぜこの宇宙は存在しているのか」という発問を荒っぽく構成要素に分解してみると、「なぜ」「この・宇宙」「存在」というふうになるね。じゃあこれらの発問要素をめぐって何か確実に「了解」されている共通的特質があるか、考えてみよう。
「なぜ」って何なのさ、「この・宇宙」っ何なのさ、「存在」って何のさ、あんたあの子の何なのさ(笑ったかな、というより理解できたかな)。
それだから、答えられないことは聞くな、という俗流の応答様式には、それなりの根拠がある。答えられないことは聞いても答えられない。これ以上さっぱりした言明はないよ。
答えられないことは沈黙しなければならない。「なぜこの世界が存在しているのか」という問いを満足させうる知的資料は存在しない。『創世記』を開いても『神学大全』を開いても『利己的な遺伝子』を開いても『存在と無』を開いても分からない。永久に。いかなる発問においても、知的欲求不満は必至なのだ。この辺はいずれもっと詳細に述べようと思う。問いの中には問いがマトリョーシカ人形みたいに構造化されている。というより、上記の理由で問いそのものの足腰が弱すぎて曖昧性を免れえない。
私見だけど、「人間の生きる意味」などを飽きずに問い続けるより、この「問うことの不可能性」を微細に分析し続けるほうが、知的パフォーマンスにおいてより大きいと考えています。問うことは答えること以上に難しい、というより不毛である、という認識。何かを確実に知りたいという欲求に憑かれるのはつらいことだろうけれど(満たされないから)、それでも問うことをやめないのが人間の性。人間だもの(いや人間って何んだ)。
ずっとずっと「最終言明」の幻を追い続けるのも一興じゃないですか。問うことの欺瞞と曖昧を凝視しつつ、しかし問うことに一縷の望みを愚直に追い求め続けるのも。オアシスを求めつづける沙漠のキャラバンのように(こんな月並みの直喩しか思いつかないのか)。
自分の「確信」や「直観」をひたすら「括弧」に入れ続ける勇気を欠いた人間は、哲学者にはなれない。思索者にもなれない。その真似事さえできない。
「創造主がつくられたから」というふうな出来合いの形而上学的命題をひたすら再生産していれば事足りる「宗教者」より、やはり、こういう過酷な宙吊り状態に耐えられる思索者に僕は憧れるのだ。
いちどデカルトに対面して、 思索に耽ってみてください。